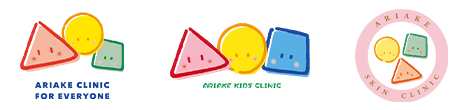乳幼児の鉄欠乏性貧血とは?~健やかな成長のために知っておきたいこと~
こんにちは。今日は乳幼児の健康にとって重要なテーマ、「鉄欠乏性貧血」についてお話しします。実は、多くの研究で、乳幼児期の鉄の状態が、その後の成長や発達に大きく関わることが明らかになっています。
まずは、いくつかの信頼できる研究から、わかってきたことをご紹介します。

🔍 論文からわかる鉄欠乏性貧血の影響
- 症状が出にくい“かくれ貧血”もある
米国小児科学会の報告では、貧血の症状が見られなくても、鉄が不足しているだけで神経の発達に影響が出る可能性があるとされています
(Baker & Greer, 2010)。 - 鉄は成長に必要な栄養素
国際的なレビュー論文では、早産児や低出生体重児における鉄不足のリスクが高く、栄養管理の重要性が強調されています
(Mahmoud, 2024)。
鉄欠乏性貧血とは?
鉄欠乏性貧血とは、鉄が体内で不足し、赤血球をうまく作れなくなる状態です。赤血球は酸素を運ぶ役割があるため、鉄が足りないと酸素が全身に行き渡りにくくなります。
乳児は急速に成長するため、鉄の必要量が多く、特に生後6ヶ月以降は母乳だけでは鉄が不足しがちになります。そのため、離乳食での鉄の補給が大切です。
どんな影響があるの?
鉄欠乏性貧血の初期には、明らかな症状が出ないこともありますが、長期的には次のような影響が報告されています:
- 成長のスピードが緩やかになることがある
- 運動機能や注意力の発達に影響が出る場合がある
- 食欲が落ちたり、集中力が続きにくくなることもある
これらは、すぐに病気というわけではありませんが、栄養の状態を見直すサインになることがあります。
どうすれば予防できる?
以下のような生活習慣で、鉄欠乏性貧血の予防が期待できます。
- 生後6ヶ月ごろから、赤身の肉や魚、大豆製品など鉄を含む食品を取り入れる
- 離乳食の進み具合に応じて、必要なら鉄のサプリメントを検討(特に早産児・低出生体重児)
- 牛乳は1歳までは控えめに(鉄の吸収を妨げることがあります)
成長発達が良好な赤ちゃんは心配しすぎないでくださいね
健診では、お子さんの身長や体重、発達の様子をしっかりフォローしています。その中で、もし成長や発達が少しゆっくりかな?と感じられる場合に、必要に応じて鉄の状態を調べることがあります。
ですので、すべての赤ちゃんに必ず血液検査を行うわけではありません。順調に育っているお子さんについては、基本的にはご心配いりません。医師がその子の成長の様子を見ながら、必要がある場合にだけ検査をおすすめしています。
【院長コメント】歴史から学ぶ“土台の大切さ”
健診では成長発達をフォローしておりますが、そのときにすこし緩やかなお子さんだと調べるのがこの鉄欠乏性貧血となります。なので成長発達が順調なあかちゃんに全例血液検査!というわけではないのでご安心ください。鉄という栄養素は、小さな体にとってまさに「土台を作る石材」のようなものです。これは、法隆寺の五重塔で使われている心柱(しんばしら)にも例えられます。目立たないけれど、全体をしっかり支える大黒柱。もしそれが不足すれば、見た目は問題なくても、構造そのものに影響が出てきます。
お子さんの将来を支える“体と心の基礎づくり”に、鉄は欠かせない栄養です。怖がらず、でも油断せず、日々の食事と健診を通じて、私たちと一緒にサポートしていきましょう。