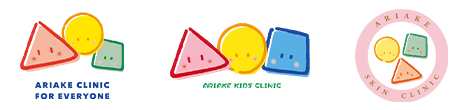こどもの溶連菌感染症について -症状・感染しやすい年齢・治療法・合併症-
皆さまこんにちは。本日は、お子さまに多くみられる「溶連菌感染症(溶連菌性咽頭炎)」について、最近の知見をもとに分かりやすくご説明申し上げます。特に、親御さまからのご相談が多い「どのような症状があるのか」「何歳頃に多いのか」「どのように治療するのか」「注意すべき合併症」について解説いたします。

🔎 近年の研究から
まず、国内外の最新の研究結果を簡潔にご紹介いたします。
- 溶連菌感染症は主に5歳から15歳の児童に多く、のどの痛み、発熱、リンパ節の腫脹が典型的症状とされています (Martin, 2015)。
- 2歳未満の乳幼児では感染の頻度が低く、陽性であっても保菌者であることが多いとされています (Amir et al., 1994)。
- 治療にはペニシリンやアモキシシリンが有効で、適切に使用することで症状の改善、合併症予防、周囲への感染拡大防止が期待できます (Kim, 2015)、(Tadesse et al., 2023)。
- 近年の研究では、抗生物質による治療は症状軽減の効果が限定的であり、必要に応じた慎重な適用が重要とされています (Gualtieri et al., 2024)。
- 抗生物質治療によりリウマチ熱や腎炎といった深刻な合併症の発症は大幅に減少しています (Shulman & Tanz, 2010)。
症状
溶連菌性咽頭炎の主な症状は以下の通りです。
- 急性の咽頭痛
- 発熱
- 嚥下困難(飲み込みにくさ)
- 頸部リンパ節の腫脹・圧痛
- 発疹(猩紅熱様発疹)を伴うこともあります
通常、風邪と異なり咳や鼻水は目立たないのが特徴です。この点が診断上の重要な手がかりとなります。
感染しやすい年齢
5歳から15歳の学童期が最も感染しやすいとされますが、2歳未満の乳幼児では感染自体が少なく、仮に検査で陽性であっても「保菌状態」であることが多いと考えられます。
治療法
診断には迅速抗原検査(のどぬぐい検査)または咽頭培養が用いられます。診断が確定した場合には、ペニシリン系抗生物質が第一選択となります。通常10日間の内服が推奨され、しっかり飲み切ることで再発防止と周囲への感染拡大防止が可能となります。
ただし、抗生物質治療は「必要な場合に限定して使用する」という原則が近年重視されています。医師による的確な診断と判断が重要です。
合併症
抗生物質治療の普及により、以前は恐れられたリウマチ熱や腎炎などの合併症は著しく減少しました。それでも適切な治療を怠れば、まれにこれらの重篤な合併症が発生することがありますので、注意が必要です。
院長コメント👨⚕️
溶連菌感染症は、まるで「能楽」のようだと思います。舞台上では静かに見える能の演者も、実は面の下でしっかりと感情を隠し持っています。同じように、この感染症も「普通の風邪のように見えて、油断すると見えない合併症という一幕が待っている」ことがあります。私たち小児科医は、冷静にその「面の裏側」を見抜き、必要なときに適切な治療を行うことが重要です。お子さまの健やかな成長を願い、保護者の皆さまと二人三脚で歩んでまいります。